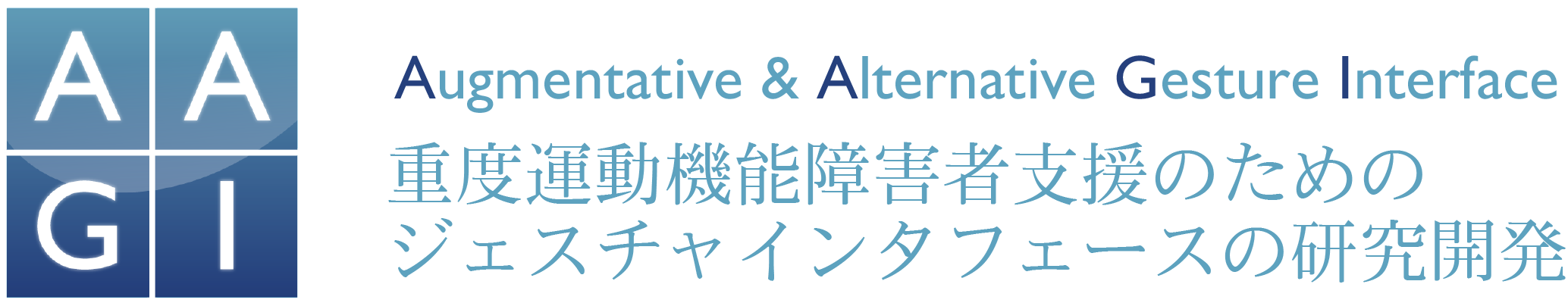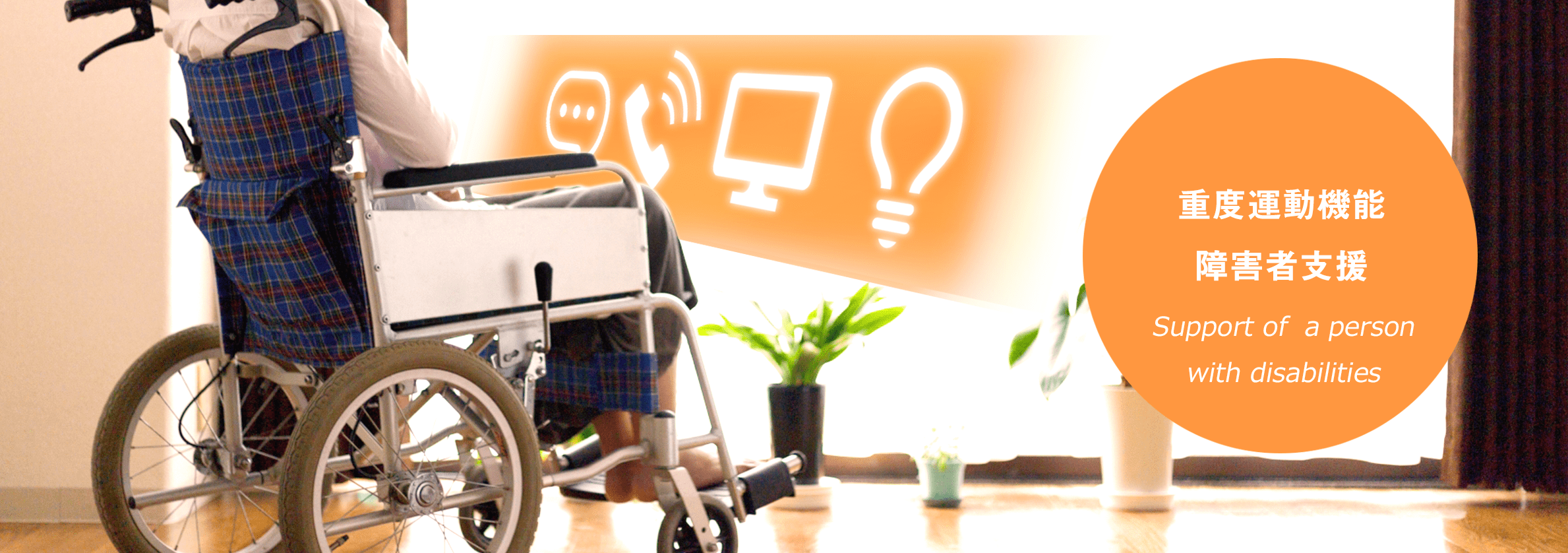重度運動機能障害者の現状
痙性や不随意運動により、既存の機器を使うことができない重度運動機能障害者は、パソコンでのメール・WEBの利用が困難なだけでなく、各種家電や携帯電話等の操作にも日々不自由な生活を送っています。運動機能障害者用のスイッチも様々な方式、種類が市販化されていますが、使用可能な機器が存在しない、または極端に限られ、特別にカスタマイズしたスイッチ形式の機器しか利用できない人々にとっては、簡易にパソコン操作等をすることができないだけでなく、緊急時に介助者がいなければ携帯電話すら利用できないという現実があります。
何が問題で、何が求められるのか?
障害の程度や不随意を伴う場合などは、操作スイッチの適合作業が上手くいかなかったり、時間がかかったりするケースが多いです。しかも、経年変化に伴う残存する障害者本人の身体機能の変化に対応するコストも大きいです。例えば、進行性筋疾患あるいは神経疾患を伴う運動機能障害者の場合、進行に伴い筋力低下などが起こります。そうなると、それまで使用していた機器などが徐々に利用できなくなり、新たな入力方法を検討し、試す適合作業が必要となっています。このようなケースでも、ユーザの個々の身体特性と長期的な変化に適応する機器が求められています。
個人適応の必要性
障害者は障害の程度や随意の部位、不随意運動の入り方など多種多様で、1つの方式で対応することは、そもそも無理があります。一方で、個人が全員違うからといって、全てに対応する機器やソフトウェアを開発することも、無理があります。そうなると、ある程度の複数の雛形となるものは用意する必要性と、個人の動きの大きさなどを学習する必要性が同時に生まれます。